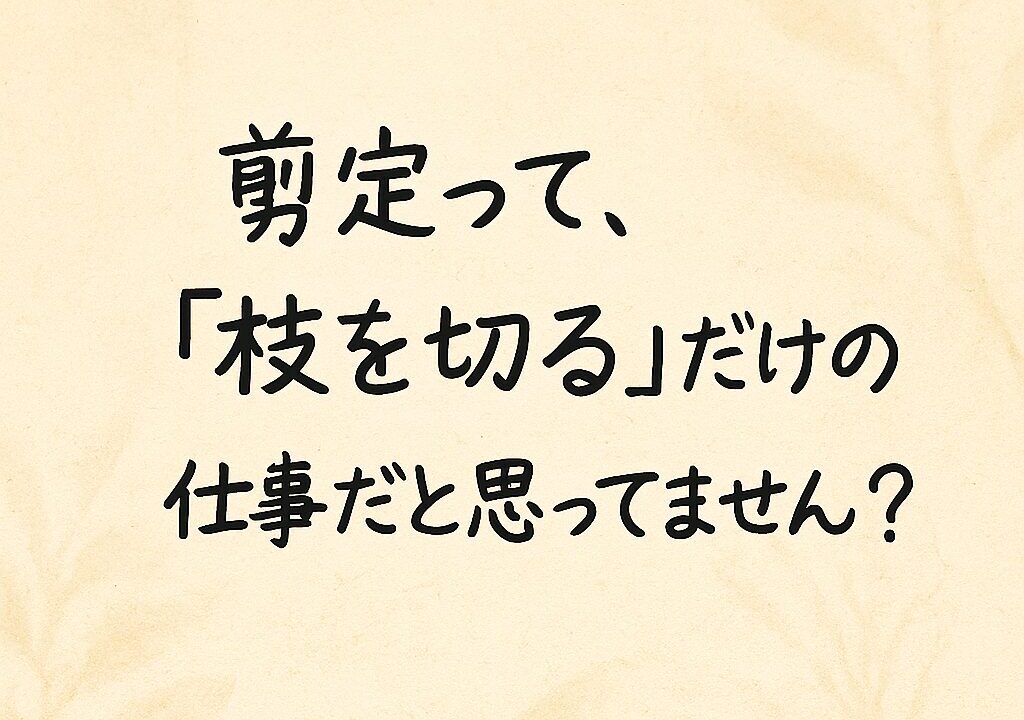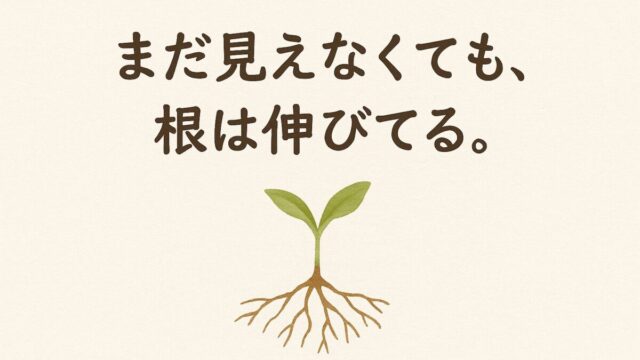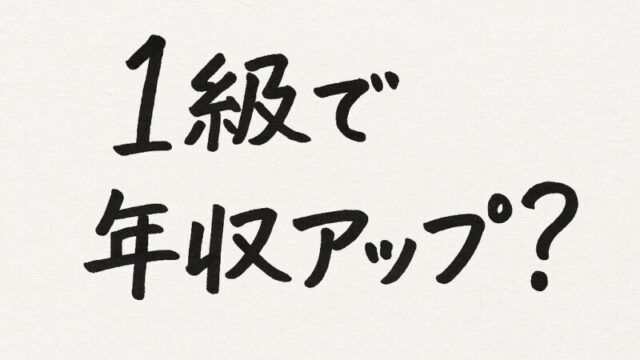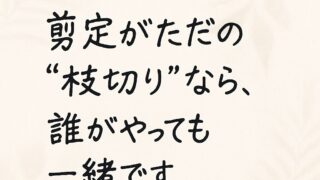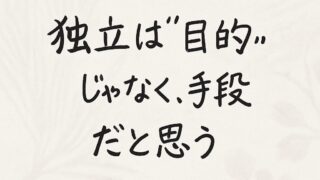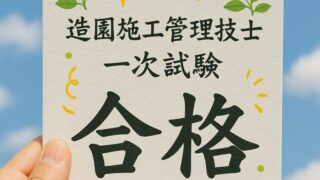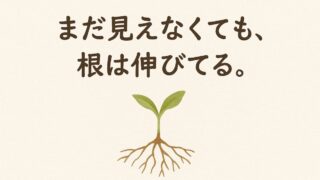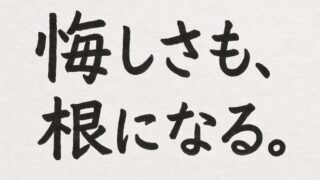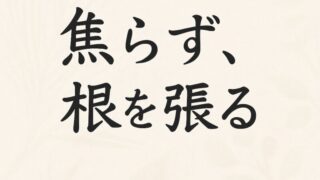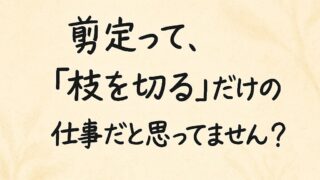植木屋の世界では、「剪定の腕は見ればわかる」とよく言われます。
たしかに、技術の高い剪定は、仕上がりが美しいし、翌年の伸び方も違う。
でも僕は最近、「技術だけじゃ足りないな」と思うことが増えました。
それは、“気配り”があるかどうか。
そして、その気配りが剪定の仕上がりにも、お客さまの満足度にも、大きく関わってくるのです。
⸻
「おばあちゃんが落ち葉で滑るんです」から始まった話
ある日、剪定のご依頼をいただいたお宅へ伺いました。
玄関まわりには立派なモミジ。
でも落ち葉がすごくて、秋口になると毎朝掃除が大変なんだとか。
「この前、おばあちゃんが落ち葉で滑りそうになってね…」と、奥さまは心配そうな顔をしていました。
落葉樹があると悩みの種になりますね。毎日落ち葉掃除をするのは大変なことです。かといってほったらかしにしていると、お庭はどんどん綺麗ではなくなっていきます。

そこで剪定の技術だけで考えるなら、「混みあってる枝を間引いて、風通しをよくする」「夏場の強剪定は避けて…」というセオリーどおりの剪定になります。
でも、このとき大事なのは“誰がどこをどう困っているか”という気配りなのではないかと考えます。
「こっちの通路側はなるべく葉を落とさないよう切ろう」
「玄関前は枝を少し上げて、風で落ち葉が吹き込まないようにしよう」
ほんの少しの工夫かもしれないけど、
それだけで「助かりました!」と、心から感謝される剪定になるんです。
剪定は一回やったら終わりというわけではありません。今年で一気に切るのが木にとって良くないこともあります。そんなときに大事なのがコミュニケーションです。
作業の説明、次回の剪定や来年度の剪定のときはこう考えているなど、しっかりとした説明があれば施主さんも安心して任してくれます。
⸻
“見えない配慮”こそが職人のかっこよさ
植木屋の技術って、どの枝を切るかや、ノコギリの入れ方だけじゃありません。
たとえば、
- ご近所に枝が落ちないようにシートをかける
- あえて剪定した花や葉を手水鉢に浮かべる
- 作業音が大きくなりすぎない時間帯を選ぶ
- 消毒作業中はお客さんの車に飛ばないように向きを変える
- 落とした葉を残さず片付ける
こういった“見えない配慮”こそが、職人の本当のかっこよさだと思うんです。

そしてそれは、お客さまに対する「気配り」がないと生まれない。
僕は、剪定が終わったあとにお客さまが庭に出てきて、
「なんか、前より風通しがよくなった気がする」
「おばあちゃん、玄関の階段が歩きやすくなったって喜んでました」
そんな言葉をくれたとき、やっと「よかった」と思えるんです。
作業の+1を常に心がけ、日和舎さんに頼んでよかったと心から思ってもらえるような植木やさんになりたいと思っております。
⸻
「ただの枝切り屋さん」で終わらないために
剪定って、言ってしまえば“木の枝を切る仕事”です。
でも、その枝を切る“手前の理由”と“先の暮らし”を考えられるかどうかで、ぜんぜん違います。
たとえば、
「この枝は来年どう伸びるか」だけじゃなく、
「この枝を残すと、ここに木陰ができて、おばあちゃんが腰掛けやすくなるな」
とか、
「ここは西日が強いから、あえて少し葉を残しておこう」
「リビングから一番見えるところやからあえてボリュームを残しておこう」
そんな想像ができるかどうか。
それって結局、“人を見る力”や“想像力”または“思いやり”だったりするんですよね。
つまり、「技術」だけじゃなく「気配り」と「心づかい」が合わさって、はじめて“いい仕事”になると考えています。

夫婦関係や恋人関係もそうですよね。「やってあげた」や、「感謝してや」という押し付けたような感覚では上手くいきませんよね。
「させていただきました」なんだったら何も言わずさらっとやってるほうがスマートでかっこよくないですか?
⸻
「気配り」もまた、経験で育つ技術
もちろん、最初から全部できたわけじゃありません。
僕も新人の頃は、「とにかく切って、片付けて、終わり!」という感覚でした。
早く帰って遊びたいですしね(笑)
でも、何年か経験を重ねる中で、
「あれ? このお宅、こんなお庭暗かったっけ?」とか、
「このご家族、お子さんが中学校にあがったんや」とか、
ふとした気づきが増えていったんです。
それに気づけたとき、剪定がただの作業じゃなく、“その人の暮らしをサポートする行為”になった気がしました。
それがなぜか気持ちよくて、もともとお話するのが得意ではなかったんですけど、世間話を通じて仲が良くなるというか信頼されていってるんかな?という感覚は気持ちがいいものです。
だからこそ、僕は「気配り」も“技術”と同じくらい、経験とともに育っていくものだと思っています。
⸻
「日和舎」が大切にしている働き方
僕が「日和舎(ひよりや)」という名前を掲げたのも、こうした“働き方のスタイル”を大事にしたかったからです。
日和という言葉には、「いいお天気の日」だけじゃなく、「何かを始めるのにふさわしい日」という意味があります。
僕は、剪定を通じて“暮らしの中の小さな日和”を届けたい。
それは、「ちょっとだけ光が入るようになった朝」とか、「庭がきれいになって気持ちよく始まる休日」とか。
そんな日々のきっかけを作る仕事だと思っています。
植木を通じて毎日をポジティブに明るく過ごしてほしい。喧嘩してても水やりを一緒にして仲直りしてほしい。お子さんの感性を磨いていくきっかけになればいい。
何よりも僕に会って、人生がちょっとでも明るくなったと思ってもらえることが、何よりも幸せです。
→こちらにも僕の思いを綴っていますのでぜひ見ていってください。
⸻
✂️まとめ|剪定は、暮らしへの“気配り”が宿る仕事
「腕がいいだけじゃない」「切るだけじゃない」
植木屋という仕事の奥深さを、年々感じています。
剪定には、確かな技術が必要です。
でも、それだけじゃ足りない。
気配りや想像力、思いやり。人の暮らしに寄り添う気持ちがあってこそ、本当の“良い剪定”になる。
これからも僕は、ただの“木を切る人”ではなく、
「この人に頼むと、暮らしがちょっと良くなる」
「あの人かっこいい。早く会いたい」
そんな風に思ってもらえる職人でありたいと思います。
例えば、ふとした休日の朝、「木漏れ日気持ちいいな」と感じてもらえるような、
そんな剪定ができたら嬉しいです。
⸻
🌿読んでくださったあなたへ
この記事では、「剪定の仕事に活きる“気配り”」というテーマで、
僕なりの働き方や大切にしている想いを綴ってみました。
技術だけではなく、人と暮らしに向き合う。
そんな植木屋の在り方を、これからも「はたらく日和」で発信していきます。
また次回も、のぞいてもらえたらうれしいです。
Instagramを開設しましたのでこちらも気軽に見ていってください。