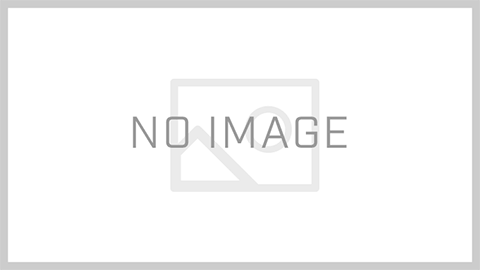秋から冬にかけての庭仕事チェックリスト|植木屋が解説する来年に繋がる庭支度

秋になると、庭は一気に表情を変えます。
紅葉に染まる木々、落ち葉でいっぱいの地面、そして朝晩の冷え込み。
そんなとき「庭の手入れをそろそろしなきゃ」と思うけれど、実際にはこんな悩みが多いはずです。

- 剪定って今していいの?
- 落ち葉はそのままでも大丈夫?
- 新しい木を植えるなら春じゃないの?
実は、秋から冬にかけての庭仕事は「来年の庭をどう楽しむか」に直結します。
今回は、庭師としての経験に加え、専門資料を交えて「秋〜冬にやっておくべき庭仕事」をチェックリスト形式でまとめました。
| 作業内容 | ポイント | 注意点・補足 |
|---|---|---|
| 剪定 | 秋は軽剪定で整える程度 |
・常緑樹(ツバキ・サザンカ):花芽を落とさない ・落葉樹(モミジ・カエデ):落葉後に軽く整える ・本格剪定は冬(12〜2月) |
| 植え替え・新植 | 秋は根が落ち着きやすくベスト | 春よりも管理がしやすく、活着率が高い |
| 落ち葉掃除 | こまめに集めて清掃 | ・病害虫の温床を防ぐ ・腐葉土や堆肥に再利用できる |
| 害虫・病気対策 | 越冬前に卵や病葉を処理 | ・チャドクガ:卵を落とす ・カイガラムシ:枝に残さない ・病気葉は翌年に持ち越さない |
| 水やり・肥料 | 乾いたらしっかり水を与える | ・秋は根が伸びる時期 ・冬前に寒肥を準備(2月頃に施肥) |
✅ 剪定は“軽く”でOK、本格的なのは冬に
秋は花芽をつける木が多いため、強剪定は避けるのが基本です。
- 常緑樹(ツバキ・サザンカなど)
→ 秋に強く切ると花芽を落とし、翌年の花が減る。 - 落葉樹(モミジ・カエデなど)
→ 紅葉を楽しんだあと、落葉期に軽剪定で枝ぶりを整える程度。 - 高木や大きな庭木
→ 無理に切らず、冬の休眠期(12月〜2月)にプロへ依頼するのがおすすめ。
👉 園芸学会の研究でも「花芽形成期の強剪定は開花数の減少につながる」と明記されています(参考:園芸学会雑誌 第87巻)。
もっと詳しい剪定の違いは、過去記事
➡ 雑木の庭を台無しにしないために|剪定方法の違いを解説
でまとめています。
✅ 植え替え・新植は秋がベストシーズン
「木を植えるなら春」と思われがちですが、実は秋こそおすすめです。
- 土の温度が安定していて根が落ち着きやすい
- 夏の暑さがなく、管理がしやすい
- 活着率が高く、庭木にとって負担が少ない
紅葉樹を取り入れたい方や庭をリニューアルしたい方は、この時期がチャンス。
おすすめの紅葉樹は、過去記事
➡ 紅葉の種類について|庭木としておすすめの代表樹
も参考にしてみてください。
✅ 落ち葉掃除は“来年への投資”
秋の定番といえば落ち葉掃除。「やってもやっても終わらない…」と感じるかもしれません。

- 放置すると病害虫の温床になる
- 濡れ落ち葉は滑りやすく事故の原因に
- 集めた落ち葉は腐葉土や堆肥に活用できる
👉 農林水産省のガイドラインでも「落ち葉堆肥は有機質肥料として有効」と紹介されています。
「ただの掃除」ではなく「来年の肥料づくり」と考えると、庭仕事がぐっと楽しくなります。
✅ 害虫・病気対策は“越冬前”に
秋は害虫や病気の“仕込みの時期”。今のうちに手を打っておくと春がぐっと楽になります。
- チャドクガ → ツバキやサザンカに卵を産みつけて越冬
- カイガラムシ → 幹や枝にくっついたまま冬越し
- 病気の葉 → そのまま残すと翌年に再発
庭木と害虫の付き合い方については、過去記事
👉 アシナガバチとの付き合い方|夏の暮らしを守る知恵
👉【要注意!】チャドクガの危険性と安全な駆除方法|庭木と暮らしを守る知識
で自然とのバランスも解説しています。
✅ 水やりと肥料
「秋は涼しいから水やりはいらない」と思いがちですが、実は根がしっかり伸びる時期です。
- 土が乾いたらたっぷり水やり
- 冬に入る前に「寒肥(かんごえ)」を準備(2月頃に与えると芽吹きが良くなる)
こうした小さな積み重ねが、翌年の庭の姿を大きく変えます。

まとめ|秋冬の庭は“来年の準備期間”
秋から冬にかけての庭仕事は「片付け」ではなく「準備」です。
軽剪定・植え替え・落ち葉掃除・害虫対策・肥料準備。
それぞれは小さな作業ですが、来年の春に庭を見たときに「やっておいてよかった」と必ず思えるはずです。
日和舎では「庭を整えると、暮らしも整う」を大切にしています。
🍃 秋の庭仕事を楽しんで、来年の春をもっと待ち遠しくしましょう。